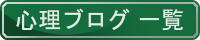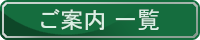『イド』 と『 超自我』。
オーストリアの精神科医
フロイトが
約100年前に考えた概念です。
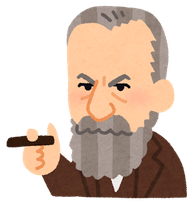
イドと超自我
『イド』とは、
衝動的になにかを得ようとする働き。
『超自我』は、
イドに対してダメダメと禁じようとする働き。
心の中では
『イド』と『超自我』がせめぎ合っている
とフロイトの考えました。
ここからは私説
「イド?超自我?この説明で本当に合ってるの?」
という疑問は、私にもありました。
心理学の開祖フロイトの理論とはいえ、
私も学者のはしくれ、
悩みの深さの特に深いところを説明するものとして、
徹底的に掘り下げていったのです。
そして、今では次のように説明しています。
イドと、超自我は、
人間の心に もともと組み込まれている
ふたつの生存戦略と合致していると考えたのです。
ふたつの生存戦略
我々人間の遺伝子には、ふたつの生存戦略が設定されています。
ひとつは、個人単独で生き延びようとする考え方です。
もうひとつは、群れの一員でいることで生き延びようとする考え方です。
普段は意識しなくとも、このふたつが本能的にあるはずです。
両者のバランスが心のバランスにもなっているでしょうし、
個性や生き方にもなっているでしょう。
この両者は、複雑に絡み合っていて、
時には心の中でせめぎ合ってしまうものです。
また、どちらに関しても、うまくいったり・いかなかったりします。
片方がうまくいかないと人は、もう一方の戦略に頼ろうともするでしょう。
そして、どちらもうまくいかないと、ひどく苦悩を感じるものです。
今回のブログでは細かくは説明できませんが、
「誰もひとりでは生きられない」(※1)という歌があったり、
「生きてく時はひとりだ」(※2)という歌があったりして、
どっちだという話ではない、永遠のテーマなのです。
群れにいる意義は、太古の昔だとより深刻だったと思われます。
群れの中に居なければ、マンモスの肉にありつけない、みたいな…。
今だと別に群れの中に居なくてもコンビニでおにぎりが買えますが、
遺伝子には「群れに居ろ」という指令が残っていて、
集団・他者・所属を良くも悪くも意識するわけです。
そして、所属集団(家族、学校、地域社会など)の心への影響を物語るところでもあります。
個人としてのわがままな生存本能(イド)。
群れを意識する生存本能(超自我)。
ふたつの生存本能は、心の中で複雑にせめぎ合っているのです。
超自我も生存本能であった
従来の理論では、
イドとは生に積極的な欲動であり、
それに対して
超自我はブロックしようとするものと
位置付けられてきました。
あらためて、
超自我もまた別の意味での
生存本能による生存戦略を担っていたと
とらえなおすことで
心の現象はより説明がつくのではと
考えるようになりました。
超自我の働きによって、
所属する群れの強者を意識しますし、
群れから外されそうな動きに対しては強い抵抗を示すのです。
心理カウンセリングのご案内
心の中で、
何が起きているのか、
どうバランスをとろうとしているのか、
一緒に確認していきましょう。
フロイトによると、
人は思っているほど自分の意思で生きられているわけではなく
心の無意識から多くの影響を受けているのだそうです。
個として自分を出したい←→群れに居なければ、
こうした無意識のせめぎあいに
翻弄されない心のあり方を目指していくのです。
引用
※1 『めぐりあい』(1982)歌:井上大輔 作詞:売野雅勇、井荻鱗 作曲:井上大輔
※2 『戦う時はひとりだ』(2013)演奏:忘れらんねえよ 作詞作曲:柴田隆浩
↓心理ブログ一覧はこちら
↓川越こころサポート室についてのブログ一覧はこちら
電子書籍のご紹介
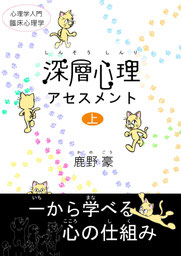
amazon kindle(電子書籍)にて発売中